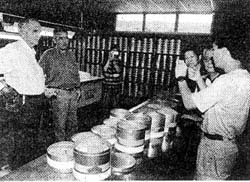ウインドファームの創立30年を振り返って(その1)
有機農法に携わる人々(前篇)(1998年11月サンパウロ新聞)より抜粋
農薬や有害化学物質などによる環境汚染、自然破壊が侵攻する今日。特に開発途上国などでは、海外からの企業進出がその要因の一つになっているケースも少なくない。そうした中で、身体に害の無い安全な生産物をつくり、消費者に提供するという動きが世界中で目立ってきている。ブラジルでも農薬の使用を減らし、有機農法を実践する人たちがいる。ここでは有機農業などに携わり、身の周りから環境破壊を防ごうとする人々を紹介する。
生産者との公正な貿易(フェアトレード)を目指し、ミナス州マッシャード市の「ジャカランダ農場」で栽培されている無農薬有機コーヒーの日本での輸入販売を、93年から始めた(有)有機コーヒー社長の中村隆市さん(43、福岡県出身)。
地元の高校を卒業後、映画監督になることを希望していたが、水俣病との出会いにより、公害、環境問題に興味を持ち、有機農産物の産直活動に取り組んでいく。
86年に発生したチェルノブイリ原発事故で被爆した、隣国ベラルーシ共和国の人々への支援を行うための運動を90年から並行して展開。その支援金を捻出するためにも、有機無農薬コーヒーの日本での販売は欠かせなかった。何より、ジャカランダ農場で働く人々との出会いが、現在の中村さんの活動を支えている。農場主のカルロス・フェルナンデス・フランコさん(七一)の無農薬の土地づくりを推進する思いが、中村さんの気持ちと一致したためだ。
今年5月末に来伯した中村さんは、農場の状況視察とともにコロンビアで初めて開催された国際有機コーヒーセミナーに出席。研究者だけでない生産者との交流を行い、現場の声を目の当たりにした。
また、10月12日からは「消費者に実際の生産現場を見てほしい」との考えから、来年から本格的に行われるジャカランダ農場の「スタディー・ツアー」の準備を兼ねて約一週間滞在。再び農場を訪問し、生産者との交流も行なった。
さらに、同じミナス州のラゴア村も訪問し、フェアトレードの可能性も探った。
中村さんによると、現在の日本では有機無農薬産品について「一過性の健康ブームという訳ではなく、総合的な環境問題を含めて、当たり前といった意識になってきている」という。
それだけ環境問題について、人々の意識が高まってきたとも言えるが、「身体に害のない美味しいものを食べたい」との考えが、消費者の中に芽生えてきたのも確かなようだ。
「ジャカランダ農場とのつながりは、単に売る人と買う人の関係だけではなく、一緒に有機農業を広げていく仲間でもあります。農薬による被害で中毒になったり、亡くなったりしている人の問題を取り上げ、環境に対する一般の意識をさらに高めていきたい」(中村さん)
中村さんの挑戦はさらに続く。
(2)
中村さんがミナス州ラゴア村の小農民の状況を視察した翌日の10月8日、有機農法博士の宮坂四郎さん(74、北海道出身)の案内でモジダスクルーズへと向かう車に記者も同行させてもらった。
宮坂さんは、7月のコロンビアでの国際有機コーヒーセミナーにブラジル代表として参加。炭を焼くことによって採取され、害虫の忌避剤にもなる「木酢(もくさく)」の効用について講義した。自然農法生産者協会(APAN)やブラジル有機農業協会(AAO)の創立に携わるなど、「有機農法の伝道師的存在」(中村さん)となっている。
(3)
「ここでは、ハウス(栽培)内に鳥が巣を作ってますよ」―。
こう語るのは、モジ群ビリチバ・ミリンでトマトを生産する鈴木啓三さん(61、山形県出身)。農薬を使用していない証拠だ。
鈴木さんは、9年間11回にわたって、同じ場所でトマトの連作を行なっている。作っているのは「桃太郎」と言われる大玉の種類だ。化学肥料を使った場合、土地が疲弊するために休ませるのが普通だが、籾殻(もみがら)を焼いた煙炭、砂糖きびの絞りかすやボカシなどの有機肥料を使用することで、土地自体に持続力が付いていく。
自然農法生産者協会(APAN)にも89年頃から入会している鈴木さんだが、それ以前から有機農法には興味を抱いていたという。「大抵の生産者は、トマトを育てることに一生懸命になっていますが、私の場合は、土地を作りあげることに力を入れてきました」
実際、鈴木さんが栽培しているハウスの中には籾殻を焼いた煙炭が一面に撒かれている。
しかし、そんな鈴木さんも有機農法に切り替えた当初は、害虫の被害にもやられた。土地自身に害虫をはねつける力が無かったことが原因だ。それ以来、農道にだけ使っていた除草剤もいっさいの使用を止めた。
「色々な人に会って話を聞いたり、有機関係の本は片っ端から読みましたね」
少しずつだが、土地に変化が現れ出した。農薬を使用する一般のハウス内には飛ぶことのなかった小鳥が飛び、巣を作るようになった。その積み重ねが、今の鈴木さんの考えを強固なものへと変えた。
「この周辺では有機栽培をやっている人はほとんどいませんね。ハウスは二、三年やるとほとんどの人は資材などの費用がかさんで続けられなくなります。化学肥料を使っていることが、却って自分を苦しめることになるのです」
現在では、化学肥料を使っていないのが「売り」となっており、市販のものより多少値段は高くても、自然な甘さが消費者に受けている。記者自身も賞味させてもらったが、まだ表面は青さが残っていたものでも、内部は柔らかく、濃い甘みがあるのが印象的だった。
ブラジルではまだ有機農法は一部にしか認識されていないが、鈴木さんは「『有機農産物を作るのは当たり前』という方向に必ずなるでしょうね」と自信を見せる。
「土壌を作るといっても、実際には微生物がやるんです。それをいかに我々が手を加えてやるかなんです。今まで多かれ少なかれ、いじめてきた土地を元に戻す作業を今やっている訳です」
「桃太郎」種のトマトは最近ブラジルでも値段も安定し、美味しいのが定評となっているが、生産が難しいという。
「難しければ難しいほど、またそれが面白くなって止められないんですね」と鈴木さんは笑う。心から農業を大切にし、楽しんでいる姿がそこにはあった。
(4)
モジダスクルーゼスで有機農法に携わる人たちを訪ねて同行した記者は最後に、ビリチーバ・ウス郡にある宮坂氏の別荘に案内してもらった。
そこには現在、宮坂氏の娘のロザーナさん(34、二世)と夫で大工仕事を行う海老根盛人(えびね・もりと)さん(32、栃木県出身)が住んでいる。場所は「人里離れた森の中」といった感じで、旧家を建て直して生活しているという。
海老根さんは元々、家具職人として神奈川県で職業訓練校の教師を養成する「職業訓練大学校」に勤めていたが、本格的に家具作りに取り組むため、栃木に移り住んだ。その合間に「創造の森」という有機農業による畑を自ら作り、野菜など40種類におよぶ生産物を栽培していた。その時に日本に就労していて知り合ったロザーナさんと結婚。並行して、有機生産物を使用したレストランも経営した。
その後、96年にブラジルに移住する決意を固め、現在の場所で大工仕事の注文を受けながら生活している。
しかし、移住した当初やりたかった有機栽培は仕事が忙しいために中断しており、「暇を見つけて続けたいのですが」と海老根さんは苦笑する。
自然とともに生きることをモットーとする「シュタイナー教育」に「少なからず影響された」という海老根さんは、少しずつ自分の考えを実践する。
海老根さんは家具職人としてブラジルで働く中で、一つのポリシーを貫く。それは、「無垢」(むく)と呼ばれる一本木を使うことだ。
「ブラジルで販売されている家具はそのほとんどが、合板が使用されています。表面は見栄えがいいですが、良い接着剤を使わなければすぐに剥がれてきます。それに比べて無垢では、五十年、百年たっても壊れません」
さらに海老根さんは、釘やネジなどを使わない日本建築の手法を重視する。例えば、机などはネジでとめると割れたり、素材そのものが曲ったりするが、木を組み合わせることによって、気候の変化に対応して伸び縮みできるようにできるという。そのためにも、無垢の素材を探し、保管・使用することは海老根さんにとって、最大のテーマでもある。
また、海老根さんが作業場を山中に選んだのは無垢によって出る木クズを畑の肥料などに再利用することにある。
「都会で大工仕事をしていると、木クズが大量に出てその処理に困りますが、ここでは畑の肥料としても使えるし、一石二鳥ですよ」と海老根さんは、限りある資源を再生することを重視する。
海老根さんは、障子の桟(さん)を削る鉋(かんな)など日本でも最近では使用されなくなった大工道具も、ブラジルに持参してきた。「昔は手作りの道具もたくさんあったのですが今ではブラジルでも電動工具が主流になり、職人のレベルが低くなっています」
いかに、自然の理にかなった家具づくりを行うか。仕事だけでなく、日々の生活の中で海老根さんは、常にこのことを考えている。(つづく)
(1998年11月サンパウロ新聞掲載)
(5)
モジを訪問した翌朝、無農薬コーヒーを生産する「ジャカランダ農場」を訪ねるべく、中村さんたちと一緒にミナスジェライス州マッシャード市に向かった。
この日、同行したのは、ジャカランダ・コーヒー友の会会長で、来年の農場への「スタディー・ツアー」を前に、「ぜひ現場を見てみたい」と自費参加した村田久さん(63)と和子さん(52)夫妻と農場には初めて行くという宮坂さん。それに(有)有機コーヒー社のブラジル側スタッフで、ミナス州ラゴア村の小農民に有機農業による自立支援に力を入れているクラウジオ牛渡さん(29、二世)というメンバー。
サンパウロ市内のチエテ・バスターミナルから約三時間半。マッシャードに着いた我々を農場主のカルロス・フェルナンデス・フランコさん(71)がスタッフとともに出迎えてくれた。
農場近くにあるカルロスさんの別荘で休憩したあと、午後から市内の農業大学とジャカランダ農場のコーヒーが選別・保管されている「DINAMO社」に案内される。
大学内にはコーヒーの苗木も育てられており、カルロスさんの口添えにより、ジゼリー・ブリガンテ学長が校内を案内してくれる。
続いて見学させてもらった「DINAMO社」には、マッシャード周辺の五十におよぶ生産農家のコーヒーが保管されている。会社側の説明では、有機無農薬のものを扱っている生産者は、わずかに数家族に満たないという。
その中でもジャカランダ農場から出荷されるコーヒーは、品質もトップクラスで、化学肥料を使用したコーヒーと混ざらないように配慮されている。
昨年、ジャカランダ農場では、天候不順とコーヒーの木の老朽化で四百俵しか収穫できなかったが、今年は二千俵と元の収穫量を取り戻した。現在、カルロスさんは、DINAMO社に日本への輸出向けに千二百俵を預けているが、それらはすべて、中村さんの有機コーヒー社に直接送られる。
中村さんとカルロスさんの「環境保護を通じて次世代に希望をつなぎたい」との共通した考えが二人の人間関係を、より強固なものにしている。
最近では、マッシャード周辺の小農民の間でも有機農業に関心を寄せる動きにあり、そのことをカルロスさんは、自分のことのように喜ぶ。
夜、カルロスさんの別荘での夕食のあと、改めて各自が自己紹介を行なった。村田夫妻と宮坂さんは、訪問させてもらったことへの感謝をそれぞれ述べる。
カルロスさんは席上、農場の現状や自分の身の周りからできる環境保護の重要性を切々と語る。
「有機農業を行なっていくうえで、技術の面だけでなく、考え方も変えていかなければならない」とカルロスさん。地球の汚染が進む中で、一人でも多くの人々の環境に対する理解が必要だと強調した。
(6)
翌日、朝から待望のジャカランダ農場を見学する。総面積は273ヘクタールあり、その内の80ヘクタールが、コーヒーの生産地。残りはバナナなどが植えられている。
はじめに、カルロスさんが一日のスケジュールを確認するため皆を呼び集め、見学する行程を説明する。
天日干し場に着くと、農場で働くスタッフがトラクターに繋いだ小型のトレーラーを用意していた。その上にスタッフやカルロスさんの家族を含めた十人ほどが乗り、農場内を見て回る。
カルロスさんはポルトガル系移民の6代目。(株)ウィンドファーム社発行の「ジャカランダコーヒー物語」によると、この地でのコーヒー栽培の歴史は、1856年に入植したカルロスさんの曾祖父にあたるジョン・マノエル・フランコ氏から始まるという。それから数えて四代目となるカルロスさんは、現在でも、祖父の時代からの農場のスタッフとのつながりを大切にする。
「5年前に初めてカルロスさんに出会った時、農場で働く人々との交流があったことが一番嬉しかった」と中村さんは、生産元にジャカランダ農場を選んだいきさつを目を細めて語る。
カルロスさんの指示により、OC(有機コーヒー)地区で下車する。農場には無農薬だが有機肥料を使用していない地域もあるが、ここは100%有機無農薬の土地だという。現在のコーヒーは96年に植えられたもので、森のように茂っている。
実際に足を踏み入れて感じるのは、土の柔らかさだ。ブラジルに多い赤土の「テラ・ロッシャ」とは違い、全体に黒い土で覆われている。
カルロスさんによると、はじめのころは堆肥を撒いていたが、昨年からは撒いていないという。土中に含まれる「みみず」などの益虫や微生物が害虫の発生を防ぎ、土が柔らかいことで根が深くまで入り、水分の吸収を良くしている。また除草剤を使わずに草を刈ることで、天然の肥料となり、全体のバランスが取れるようになるとも。
この日、カルロスさんを訪ねて同行し、20年間コーヒー仲買商に携わっているという中島エジソン・サライバさん(43、三世)は「15年前のコーヒーは、その匂いを嗅いだだけで、大体の品質が分かりましたが、農薬使用して以来、試飲してみないと判断できなくなりました。しかし、カルロスさんのは、銀行融資を受ける際にも、匂いを嗅いだだけで良いものだとの信用を得ました」と品質の高さを保証する。
OC地区には、1.8ヘクタールに1万7000株のコーヒーを植えた「ジャカランダコーヒー友の会」の土地がある。
日本に出荷される高品質の有機コーヒーはすべてこの土地から採れる。
ブラジル国内では皮肉にも、これらの高品質の製品は実際には飲めないという事実がある。
カルロスさんはこのことについて、「私たちが努力して作ったコーヒーを日本の理解ある皆様に飲んでもらうことは、最高の喜びです」と意に介さない。
良いものを良い仲間と作り、理解のある人に飲んでもらいたいとの気持ちが、カルロスさんを支配している。
(7)
日本から中村さんとともにジャカランダ農場を訪問した村田夫妻。ブラジルに来たのも、初めてだ。
福岡県に会社がある中村さんの近所に在住し、その意気を感じて、カルロスさんの農場を支援する「ジャカランダコーヒー友の会」会長にもなっている。また、消費者に現場の生産作業を見てもらうことにより、「より生産者のことを知ってもらいたい」とする考えから来年、本格的に始まるジャカランダ農場への「スタディーツアー」の準備や下見も兼ねての来伯だ。
しかし、それ以上に村田夫妻がこの地を訪れたかった理由は、ほかにある。
村田夫妻は、マレーシア・イポー市のブキメラ村に進出していた日本企業が不法で出した産業廃棄物の影響で病に苦しむ子供たちの医療援助を個人ベースで続けており、その支援金確保のためにジャカランダ農場の有機無農薬コーヒーを販売している。かねてから中村さんに、農場の話は聞いていたが、「消費者に品質の良い品物を販売する以上、ぜひ自分の目で生産現場を見てみたかった」というのが、村田夫妻の考えだ。
村田夫妻は、福岡県北九州市にある三菱化成黒崎工場(現・三菱化学黒崎事務所)に勤務していたが、3年前に久さんが定年退職。和子さんも今年10月31日に退職した。
1982年4月、三菱化成は、マレーシアのブキメラ村に合弁会社を設立。現地住民には産業廃棄物の恐ろしさが知らされないまま、働く場所があるというだけで、200人の労働者が集まった。
翌83年、「ゼリーベビー」と呼ばれる骨無し状態の子供が産まれたことことから、住民の会社に対する反対運動が起きた。
三菱化成は、「モナザイト」と呼ばれる物質から自動車部品やカラーテレビのブラウン管の蛍光塗料などに使用される希土類を抽出していたが、その抽出過程で「トリウム232」という放射性物質が出ることを知っていたにもかかわらず、産業廃棄物のずさんな管理を行なっていた。
「トリウム232」の半減期は141億年もかかり、これらの事実を85年に知った村田夫妻は「まさか、自分の働いている会社がそんな危険なことをしているとは信じられなかった」とショックの色を隠せなかった。
住人は85年に住民側8人の原告により提訴。92年7月にイポー市高等裁判所で勝訴したが、翌93年12月に逆転敗訴となった。陰でマレーシア政府が圧力をかけたと見られている。
91年、村田夫妻は会社への内部告発とともに年に一回、現地を訪れ、ブキメラの子供たちへの支援活動を行うようになった。「現地で望んでいるのは、ブキメラの村内に病院を建て、せめて週に3回でもいいから、簡単な診療をしてもらいたいということなのです」(和子さん)
現在、ブキメラ村には診療所はあっても医者が常駐していない状態で、村田さん夫妻は会社を辞めた今でも支援活動を続けている。
(8)
農場を隅々まで見学したその日の夜、カルロスさんから一人一人感想を聞かれた。
村田久さんは、日本で市民団体が活動するために、物販活動を行う経緯について説明。熊本県の「チッソ」工場から排出されて人体に被害を及ぼした「水俣病」の例を話した。
それによると水俣病の支援活動者は、30年以上にわたって柑橘類の一種で熊本特産の「甘夏」を販売しているという。しかし、甘夏の味が良くなくても、消費者は支援のために買っていた人が多かった。そのため、初めは支援の気持ちを持った人でも、時が経つにつれて、その気持ちが薄れてくると売れないようになるという。
「ブキメラの支援運動も今年で七年目ですが、最初はマレーシアからカレー粉やTシャツを買ってきては販売していました。良い品物を売るというよりも、支援のために買ってもらっていた感じでした。しかし、ジャカランダのコーヒーを扱うようになってからは、いつの間にか、美味しいから買うという人が増えました。それが、そのままブキメラ村の資金援助に役立っているのです」(久さん)
また、和子さんも「中村さんからカルロスさんの話を聞いてコーヒーの販売を始めましたが、累計で100万円以上の収益をブキメラに送りました。直接ここに来てみて、益々ジャカランダのコーヒーを自信を持って売ることができるます。人間関係がうまくいかないと、仕事もうまくいかないのだと実感しました」と率直な気持ちを語る。
これまで、通訳に徹してきた牛渡さんに意見を求めた。
牛渡さんは「消費者が、『誰が作っているのか』という生産者の顔を知ることが重要だと思います。私にとっていい仕事とは、いい気持ちでやることです。その意味で中村さんとカルロスさんという二人の人間関係の中で仕事をしていることに喜びを感じます」と述べた。
しかし、農場経営が苦しいのも事実だ。今年は平年並みの収穫があったものの、ジャカランダ農場は昨年、大きな危機に見舞われた。コーヒーの木の交換時期と不作とが重なり、農場で働くスタッフの生活にも支障をきたした。
そうした中、彼らを支えたのは、日頃から行なってきたコーヒーの品質に対する自信とカルロスさんへの信頼感だった。
「スタディーツアー」の目的は、ジャカランダ農場の支援と同時に、中村さんをはじめとする関係者の新しい挑戦でもある。
この日遅くまで話し合いは続けられた。今後の農場こと、来年から始まる「スタディーツアー」のこと。果ては、原発問題から環境問題にまで至った。
同席していたカルロスさんの次女テルマさんが冗談めかして言った。
「父はマサチューセッツ(工科大学)やハーバード(大学)よりも進んでいる」
有機農業を実践しているという意味では、確かにそうかもしれない。
人類がこれから迎える21世紀にあって、環境保護は自然なあり方として見られるようになってきた。しかし、それを良い方向に継続して進めていくか否かは、一人一人の考え方による。
今回、有機農業に携わる人々を取材する中で、そのことを強く感じた。(おわり)
(1998年11月サンパウロ新聞掲載)