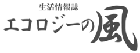新聞記者になろうとは、考えていなかった。社会の出来事を伝えるよりも、その渦中に飛び込んで活動することを望んだ。
できれば、誰も行かないような第3世界、貧困に苦しむ社会で働いてみたかった。
大学4年の時、ある研修制度を通してブラジルへ行くことにした。スラム街の自立支援に取り組む団体での研修を希望していた。
その望みは叶わなかった。自分の研修地は、サンパウロにある日系社会の邦字紙「日伯毎日新聞」。ブラジルに行ってまで、日系人を相手に記者の仕事をしなければならない。正直、そのことに幻滅した。
新聞社に出向いたその日から新聞記事を書かされた。それから、毎日、取材と記事の執筆に追われることになる。
記事を書くことに慣れると、記者の仕事に物足りなさを感じ始めた。1年の任期が終われば日本に帰る日本人。ブラジルの日系社会にあって、自分は単なる異邦人に過ぎなかった。
ただ伝えるだけでなく、人のなかに入って動きたい。たとえ記者という立場を越えてでも、そうしたかった。
きっかけをつかんだのは、ブラジルでの研修が始まってから3ヶ月が過ぎた頃、サンパウロ州グァタパラ移住地で行われた入植50周年を祝う記念イベントの取材に行った時だった。
華やかなセレモニーが催されている会場の片隅で、ある日本人移民と言葉を交わした。「こんなセレモニーよりも、日本政府はもっと真剣に自分たちのことを考えてほしい。私たちが日本人であることを認めてほしい」背景には、何の保証もないままブラジルへ渡り、作物の育たない土地に移住させられた日系移民の苦難の歴史があった。
新聞を通しての問題提起だけで終わるつもりはなかった。「いかにして、選挙権を獲得するか」選挙権を望む人々と一緒に考えた。それは、記者という立場を利用しての選挙権獲得運動だったと、幾分かの反省も込めて振り返る。
選挙権獲得という目標を共有できたとき、ブラジルの日系社会と自分の間にあった壁が取り除かれていった。日本から遠く離れたブラジルの中の日本。自分にとって新しい身内ができたような気がした。
研修の終わりが近づいたときには、日本とブラジルの間で、自分の仕事を作っていくことを決意していた。帰国後、大阪の自宅に日伯毎日新聞社関西支局を設立。その5ヶ月後には、ブラジルで交際していた日系ブラジル人3世の寛美と結婚した。
周囲の反対を押し切って設立した関西支局は、サンパウロにある本社から給料が支給されることはなかった。すべてが独立採算制。給料は自分で稼がなければならない。
日伯毎日新聞の紙面に掲載される広告を集め、またサッカーなどブラジルのニュースを日本の雑誌に売り込んで運営資金を得ようと考えた。
不況の折、広告はなかなか集まらない。新聞配達や工場で働いて生活費を稼ぐ、その一方で在外邦人選挙権に関する活動の日本側の窓口として関西支局を機能させた。
ブラジルの日系社会から始まった在外邦人の選挙権を求める運動は、北米やオーストラリアをはじめ世界中の日系社会に広まった。そして、選挙権の獲得に一応のメドが立ったとき、関西支局の活動を終了させることを考えた。子どもも生まれ、家族を養っていかなければならない。いつまでもブラジルにこだわってばかりもいられなかった。
これからの生き方を模索していた頃、関西地方を激しい揺れが襲った。6000人以上の命を奪った阪神大震災。
1995年、1月17日。その日、生後1ヶ月の長男は、朝5時頃から泣き続けていた。ミルクを与え、オムツを変えても泣きやまない。しばらくして、バーンという音ともに突き上げるような激しい縦揺れが生じた。瞬間、我が子の上に覆い被さる。子どもの命だけは守らなければ、そう思った。
地震から3日後、崩落の街へ向かう。甲子園球場の辺りで電車は進まなくなった。混乱した状況にあって、自分の目的だけは、明確だった。どうしても現場に行かなければならない。民家の庭先にいた婦人に「すみませんが」と話しかけ、事情を説明した。自分は、ブラジルの新聞社の記者であること、ブラジル人の被災状況を伝えなければならないこと。そのため、現場に向かうため自転車が必要であること。
所々で道は寸断され、倒れた電柱が行く手を阻む。その度に借物の自転車を抱えて進んだ。崩壊した高速道路には、バスの前輪が宙に浮いていた。
被災地に近づくにつれて、匂いが変わり始める。あるゆるものが焼け混じった匂いが漂っていた。
現場は、神戸市東灘区。海に近く、地盤が弱いその地域は、被害が集中していた。
1キロほど離れた所に、神戸港がある。かつてそこから、ブラジルへ移住する多くの日本人が旅立った。ブラジルで生まれたその子孫が、今この場所で命を失わなければならないことに、何かしらの因縁を感じずにはいられなかった。
亡くなった親子が住んでいた2階建てのアパートの1階は圧縮され、消滅していた。砕け絡み合い瓦礫と化した家具、ガラス戸の枠、畳、木材。その狭間に見え隠れする乳母車、枕、赤いタンスの引出し。
数日前までそこは、家族の生活が営まれていた場所だった。4人家族のうち、1人の父親と、その2人の子どもが亡くなり、母親が独り、取り残されていた。父親は、子どもに覆い被さるようにして死んでいたという。
求めていたのは、何だったのか。遠いブラジルの地から、家族で日本に来ていた。その目的は、夢は。 瓦礫の中から、冊子を見つけた。ポルトガル語で書かれたブラジルの住宅情報誌だった。それには、サンパウロで販売されている住宅の写真が掲載されていた。
はたと気付く。日本での労働の果てに思い描いていたのは、家族で住む家ではなかったのか。だとしたら、地震は、その夢を根底から破壊したことになる。さらに、その現実を、残された母親は独りで受け止めなければならない。
揺れた瞬間、自分も同様に子どもの上に覆いかぶさっていた。もしその上に家屋が崩れていたら。もし、妻の寛美が、1人、取り残されていたら。家族が待つ家への帰途、自分の存在を、はかなく虚ろなものに感じた。
地震から数日後、震災により、日系ブラジル人5人と、その子ども3人の圧死が判明。4人の入院患者がいることが確認された。
失意のまま日本を後にする遺族たちを見送り、病院の廊下では、家族たちともに手術の成功を祈った。連日、その場に身を置き、取材して記事を書き、サンパウロの本社に送り続けた。
しかし自分のなかには不満が募っていた。他に自分にできることはないのか。選挙権を求めてキャンペーンを展開したときと同様、ただ伝えるだけでは納得できない。
気がつくと、記者以外のことをしていた。
「阪神淡路大震災・被災ブラジル人支援コーヒー」を販売し、遺族への支援金を集めた。2ヶ月後、10万円の支援金を遺族に手渡すためブラジルへ。娘を東灘区で失った母親にサンパウロで直接面会した。
訪問の理由を伝えると、途端に雰囲気が重くなった。うつろな目線で遠く見ているような表情に、腰が引けそうになる。「かえって悲しいことを思いださせてしまったかもしれない」そう思いながらも正直に気持ちを伝えた。「娘さんの分までしっかり生きて下さい。僕たちは彼女のことを忘れません。また送りますので受け取って下さい」
その後も、震災の被害を受けた日系ブラジル人との関りは絶えなかった。義援金がきちんと配分されているかの確認。雇い主(ブローカー)との給料交渉。本来、与ええれるべき正当な権利が保証されているかどうかが気になった。
外国人労働者である日系ブラジル人の立場は弱い。悪質なブローカーによる搾取や厳しい労働環境など、日本という異郷の地での出稼ぎには多くの問題が含まれており、また通常の生活においても苦労は絶えない。
ブラジルで生まれ育った日系ブラジル人にとって、母国語はポルトガル語。日本語が上手く話せない人が多い。しかし顔立ちは日本人と同じであるため、全くの異郷の地であるにも関らず、外国人として見られない。「日本人のくせに、日本語も話せないのか」そんな反応に日系ブラジル人は傷つく。
ブラジル出身の妻、寛美は、日系ブラジル人が、日本で生きることの大変さを身をもって感じていた。だからブラジルから出稼ぎに来ている日系人が安心して生活するための手助けは惜しまなかった。
例えば、病院で診察を受ける際には正確な言葉のやりとりが必要になる。そんなとき、寛美と2人病院に出向いた。医療関係の難しい書類は自分が解説し、日本語とポルトガル語を使いこなすことができる寛美が、通訳として言葉をつないだ。
寛美は日本で出産した際、医師や看護婦が、妊婦をリラックスさせるためのコミュニケーションをほとんどしないことに驚いたと言う。だから少しでも友人の不安を和らげたかった。すぐに病院に駆けつけ、手を握り、ポルトガル語で語りかけた。それらの活動はすべて、ボランティア。母国から離れて異郷の地である日本で生活する仲間からお金など取れるはずもない。
日本とブラジルの間で、必要な情報を架け渡し、サポートを提供する。それは、日本人と日系ブラジル人の間に位置する自分たちにしかできないことだった。
振り返れば、ブラジルの邦字新聞社で記者として働いたことに、すべてが起因する。在外邦人の選挙権獲得キャンペーン、被災ブラジル人の支援活動。
現在はブラジルのサッカー選手を日本のプロチームに紹介するという新しい仕事に取り組んでいる。
最初、サッカーを深くは知らない自分がその仕事をすることに不安を感じた。引き受けるかどうか、迷っているときに、自分たちが出産に立ち会ったブラジル人の友人に、こう言われた。
「心配することはない。おまえがこれまで自分たちにしてきてくれたこと。それと同じことをすればいいんだよ」
仕事のテーマは変わろうとも、日本とブラジルの間という位置と、そこで果たす役割は、これからも変わることはない。
本誌 矢野 宏和